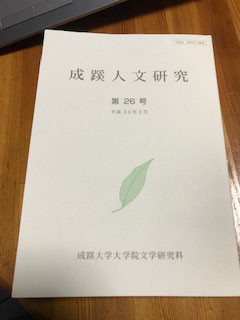昨日、成蹊大学の公開講座に参加してきました。成蹊大学文学部スペシャルレクチャーズ「日本語教育は社会にどう貢献できるか」です。
その内容はちょっと後回しにして、違うことを書きます。会場の入り口前に「ご自由にお持ちください」と紀要や論文集がありました。全部持ち帰ろうかと思いましたがたくさんあったので、目次を見ながら読んでみたいものを数冊いただいてきました。そのうちの「成蹊人文研究代26号(平成30年3月)」(成蹊大学大学院文学研究科)に収録されている「多文化社会の可能性と困難ーウィーンの社会史を通してー」(中江圭子)を読みました。
その中から気になった言葉を紹介します。
ハプスブルグの皇帝を描いたものについて
『これれの物語群は、少なくともハプスブルグの領地やあるいはウィーンという都市に生きる人びとにとっては、限りなく反復して「思い起こす必要のある伝説』であったことは確かである。』
とのくだりがありました。
わが国の「伝統的文化」や「伝統的家族像」といったものは、明治以降に形成されたものが多いようです。これもある意味での「伝説」ととらえることができたら、もっと豊かで柔軟性を持ったものが私たちの暮らしの根底、あるいは無意識下にあることに気がつくことができるのではないでしょうか。
日本文化の特徴の一つに、他文化を柔軟に取り入れ、したたかに自文化化(ヤマダ語)してきた歴史があります。それを見れば、我が国には多様に対する許容力や包容力があったはずです。そしてその多様性を受け入れることで生じる様々なストレスに耐え、乗り越えることでこそ固有の文化が鍛えられ、その価値を増すのではないかと思います。
私は、だからその時や自分の都合で歴史の一部を切り取って伝説にしない方がいい、またはしてはいけないと考えています。これって建築生産分野(設計だけでなく施工の部分も含めて)にも言えることです。
近年のIT化やAIの進歩により、建築生産分野の多くのものが様変わりすることでしょう。もちろんそのことで生じる喪失感も間違いなくあることでしょう。私も「匠の技」といったものが「簡単に」AIに置き換えられていいとは思いません。
でもね、長い時間の流れを見てみれば、社会的ニーズの変化によりそれまであったものが他のものに変わってきたように、それらを乗り越えて歴史が積み重ねられてきたというのも事実なんですね。
だからこそAIがどこまで進化していくのか、それによって生き物としての人類がどのように対応できるのかといったことを、好き嫌いでなくいったんはきちんと勉強していく必要があるのではないかと考えるところです。